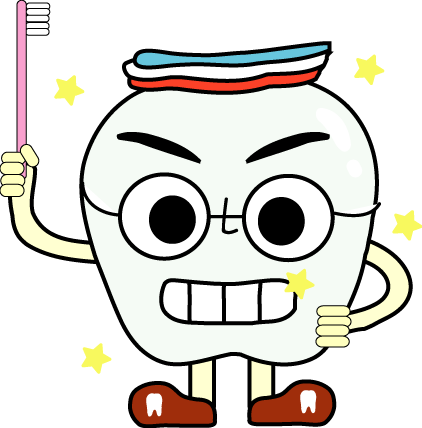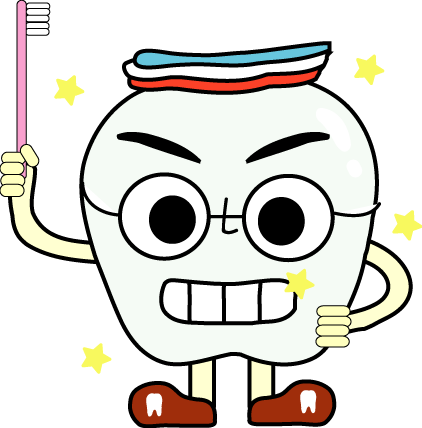
学校健診の意義
新学期が始まるとまもなく、小中学校や幼稚園などで歯科健診がおこなわれます。この際、しばしば健診の結果と、それによって
歯科医院に治療にいったときの診断が異なるときがあり、戸惑いを感じられることがあるのではないでしょうか。
このようなことが起こる理由として、現在の歯科保健や歯科医療の情勢を考慮すると、ひとつには学校保健法の改正や学習指導
要領の改訂により、学校における健診のありかたや学校保健が変わりつつあること。ふたつめには初期のむし歯の診断と治療法が
変わりつつあること。これらのことが考えられます。
1:学校健診の変化
平成7年の学校保健法施行規則の一部改正により、「疾病をみつけて勧告する」から、もう一歩進んで「疾病に移行する危険性が
高い児童生徒に対しては観察・指導を行う」、さらに「健診時に問題がない児童生徒には健康を保持増進するよう指導する」ことが
必要となったのです。このように、学校は「教育の場」であり、「医療の場」ではないことから、通常歯科医院での診断で用いられる
むし歯の確定診断名(C1、C2、C3、C4)は使用せず、部位も特定せず、「むし歯」はすべてCと表記し、むし歯の徴候や進行の危険
性のある歯をCO(シーオー)「要観察歯」とすることとなりました。つまり、歯科医院と学校とでは診断の目的が異なるのです。また、
学校での健診の環境が歯科医院のそれとでは違いがあり、特に照明は圧倒的に格差があり、あってはいけないことですが、むし歯
の見落としもないとはいえないのが現状です。
2:臨床における初期のむし歯の診断と治療法の移り変わり
「黒くて小さな穴があいている歯」をむし歯と診断しても削ったり詰めたりという 治療法を採るかどうかが近年変わりつつあるのです。
以前は、むし歯は一度なったら元に戻ることはなく、治療法もむし歯になった部分を削って詰めるのが唯一の方法だと、考えられてき
ました。しかし、むし歯は歯が溶けたり、修復されたり(再石灰化)を繰り返し、ある時点までは元に戻ったり、進行が停止したりする可
能性があることがわかってきました。ですから、歯が白く濁ったり(白濁)黒く色がついたり(着色)していても、歯質を強化したり食生活
に気をつけたり、むし歯菌を除去したりすることによって白濁が消えたり、着色が安定することもわかってきました。
但し、これはあくまでも子供たちの生えて間がない幼若な歯牙に限定され、大人の方のむし歯には該当しません。成熟過程の歯に起
きることなのです。
こうしたことから初期のむし歯の再石灰化を積極的に促進し、カリエスリスクを低くすることにより、削ったり詰めたりしないで歯を管理
していく方法(再石灰化促進療法)が新しいむし歯の治療法として確立されてきているのです。しかし、このような新しい診断や治療法
は、統一的基準となるまでには、時間がかかるのが現状です。
以上のようなことから、歯科界にもまだまだ改善、努力の余地があることは、間違いない事実なのです。